すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について
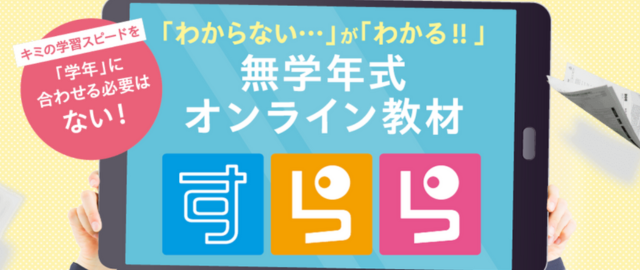
不登校の子どもにとって、「学校に行けない=出席日数が足りなくなる」というのは非常に大きな悩みです。
進級や進学、内申点に関わる問題でもあるため、保護者の不安も尽きません。
そんな中、「家庭学習でも出席扱いにできる」教材として注目されているのが【すらら】です。
すららは文部科学省が定めるガイドラインに沿った学習支援システムであり、出席認定を受けた実績も多数あります。
この記事では、なぜすららが出席扱いとして認められるのか、その具体的な理由についてわかりやすくご紹介します。
記録の信頼性や学習の継続性、学校との連携体制など、出席認定に必要な要件をどのようにクリアしているのかを徹底解説していきます。
理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
すららは、オンライン教材でありながら、学校に提出できる「客観的な学習記録レポート」が自動で生成されます。
このレポートは、学習時間、進捗、正答率など、実際に子どもがどれくらい学習したかを明確に可視化できるため、学校側にとっても信頼性が高いものと評価されています。
不登校の児童生徒が家庭でどのような学習をしているか証明することは容易ではありませんが、すららを利用すれば、保護者が記録を手書きする必要もなく、システムがすべて自動で記録してくれます。
この点が、出席扱いに必要な「学習の証明」として非常に有効に機能するのです。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
すららでは、学習した時間、単元、理解度などがシステムに記録され、それをレポート形式で出力できます。
これを学校に提出することで、ただの家庭学習ではなく「計画性・継続性のある学習」として認められやすくなります。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
多くの家庭では、不登校中の子どもの学習状況を学校にどう伝えるかに悩みます。
すららなら親が毎日記録をとる必要がなく、客観的なログが残るため、先生や教育委員会も納得しやすくなります。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
出席扱いとして認められるためには、学習の「継続性」や「計画性」も重要です。
すららでは、専任のすららコーチが一人ひとりの子どもに合わせた学習計画を立ててくれます。
学年や進度に関係なく、つまずいているところからやり直せる「無学年式」だからこそ、学校での授業の進度とは無関係に、個々の理解度に沿った学習が可能になります。
また、子どもの状況に応じて、計画を柔軟に調整できるのもポイントです。
学習が継続されている証明と、学びの内容が子どもに適したものであることを学校側に示す材料としても、すららの仕組みは非常に有効です。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
すららコーチは、ただの見守りではなく、学習の進捗に応じてリズムを整えたり、難しい単元の乗り越え方を提案してくれます。
この継続的な支援が「学習が続けられている」という実績になり、出席扱いの認定にも大きく貢献します。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
どこから学習をスタートすればよいか、どれくらいのペースが適切かは、専門家でないと判断が難しいところ。
すららでは、子どもの理解度や性格に合わせた個別の学習計画をコーチが提案してくれるため、ムリなく続けることが可能になります。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
不登校の子どもにありがちな「長期間の学習ブランク」も、すららなら問題ありません。
無学年式のカリキュラムなので、どこまで戻ってもOK。
逆に得意な科目は先取りもできるため、個々に最適な学び方が実現します。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
不登校の子どもにとって、出席扱いを認めてもらうためには「家庭」「学校」「教材(すらら)」の三者連携が欠かせません。
すららでは、必要書類の準備方法から、学校への提出用レポートの書き方まで丁寧にガイドしてくれます。
さらに、学習レポートのテンプレートを提供したり、コーチが提出書類のサポートもしてくれるので、保護者の負担がぐっと減ります。
担任の先生や校長先生とのやりとりも、すららのサポートを通じてスムーズに進められるようになります。
このような「書類だけじゃない」きめ細かな伴走が、すららが不登校支援に強い理由のひとつです。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
出席扱いを申請するには、学習時間の記録や教材の使用実績、本人の学習意欲が伝わる書類などが必要です。
すららでは、保護者が迷わないように「どんな書類が必要か」「どのタイミングで準備するのか」などを分かりやすく案内してくれます。
公式サポートのマニュアルや、学校への提出事例もあるため、「初めて出席扱いを申請する」というご家庭でも安心して進められます。
申請書類の準備に不安を感じる方にとって、心強いナビゲーターのような存在です。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
すららでは、学習記録を元にした「学習レポート」の提出も推奨されています。
このレポートは、学校側が出席扱いを判断する材料のひとつになります。
すららの専任コーチは、レポート作成に必要なデータを提供してくれるだけでなく、必要であれば提出用のフォーマットも用意してくれます。
どんな内容を書けばよいか分からない時も、コーチがアドバイスをしてくれるため、保護者の負担は最小限に抑えられます。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
学校側との連携は、出席扱いの実現において非常に重要です。
すららでは、担任の先生や校長先生との対話を円滑にするためのアドバイスや書面の準備など、現実的なサポートも行ってくれます。
たとえば「すららが文部科学省のガイドラインに準拠した教材であること」や「実際に他校で出席扱いになった事例」などをまとめた資料もあり、学校に説明する際の説得材料になります。
学校とのやり取りに自信がない保護者にも寄り添う、実用的なサポートです。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
「出席扱い」として認められるには、その教材が「学校教育に準ずるもの」として正式に評価されている必要があります。
すららは、文部科学省のガイドラインをクリアし、実際に全国の教育委員会・学校に導入されているタブレット教材です。
すららでの学習を通して、実際に出席日数として認められたケースも多数報告されています。
このように、公的機関が「学習効果あり」と判断している点がすらら最大の信頼ポイントです。
不登校の子どもにとって、「ただの家庭学習」ではなく「学校の学習の代わりになる」という証明は大きな安心材料になります。
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
すららは単なる民間教材にとどまらず、公立・私立問わず多数の教育機関に導入されてきた実績があります。
たとえば、地方の教育委員会がすららを不登校対策として正式採用しているケースもあり、「この教材なら出席扱いとして認められる」という前例が多数存在しています。
保護者が「この教材で大丈夫かな?」と不安になる気持ちに対して、こうした実績が心強い後押しになるはずです。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
すららは、公式にも「不登校の子どもを対象とした学習支援教材」として紹介されています。
学習の進捗が可視化され、コーチが個別に対応し、教材が文科省の指導要領に準拠しているという点から、学校側も導入を後押ししやすいのです。
また、すららのホームページには不登校の子を対象にしたサポート事例も紹介されており、「教材としての信頼性+活用事例」がそろっているのも安心材料です。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
文部科学省のガイドラインでは、出席扱いになるには「学校と同等レベルの学習環境が整っていること」が必要とされています。
すららは、学校の教科書に準じたカリキュラムで構成されており、教科ごとの理解度をAIが自動で分析し、つまずきがあれば即座にフィードバック。
さらに、学習レポートを保護者や学校に提出できる機能があるため、「どこまで学んでいるか」「どのくらい理解しているか」を客観的に示すことが可能です。
これらの要素がそろっていることで、学校側から「これなら授業と同等」と判断されやすくなっています。
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
すららのカリキュラムは、小中高すべてにおいて、学習指導要領にしっかり準拠しています。
たとえば国語では漢字・読解、算数では計算・文章題、英語ではリスニング・文法といった具合に、学校の授業内容とほぼ一致しているため、家庭学習であっても学習の抜けが起きにくいのが特長です。
学校の進度に合わせて柔軟にカスタマイズできる点も高く評価されています。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
すららでは、単元ごとの到達度をスコアで表示する機能があり、子ども自身も「どこが得意で、どこが苦手か」をリアルタイムで把握できます。
また、親や先生向けには、詳細な学習ログとレポートが出力できるため、「この子はこの単元を何分やって、どのくらい理解したのか」が明確になります。
こうした評価の仕組みがあることで、学校側に対しても「家庭でもしっかり学習している」という説得力ある根拠を示すことができるのです。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について
不登校の子どもが家庭で学習を継続している場合、その学びが「出席扱い」になる可能性があることをご存じでしょうか?文部科学省のガイドラインでは、一定の条件を満たす家庭学習について、学校の出席日数として認める制度が定められています。
ICT教材「すらら」は、その要件を満たしやすい教材として、多くの学校や保護者に選ばれています。
この章では、すららを使った出席扱いの申請方法について、必要な書類や流れ、注意点を詳しく解説します。
不登校のお子さんとそのご家族が、少しでも安心して学びを続けられるよう、正しい情報をお届けします。
申請方法1・担任・学校に相談する
まず最初に行うべきなのは、子どもが在籍している学校の担任の先生や、必要に応じて校長先生に相談することです。
不登校児童が「出席扱い」と認められるためには、学習状況を学校側が把握し、納得してくれることが大前提になります。
すららでの学習は「学校教育に準ずる内容」として認定されるケースが多く、学校に説明する際にはその点をきちんと伝えることが大切です。
保護者が一人で動くのではなく、「学校と協力して手続きを進める」姿勢を見せることが成功のポイントになります。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
出席扱いの申請には、「家庭学習の記録」「教材の種類」「学習時間」などの条件を満たす必要があります。
学校によって若干の違いはありますが、共通して求められるのは「客観的に学習状況を示す書類」です。
具体的には、すららで出力できる学習レポートや、毎日の学習記録表、申請書などが挙げられます。
まずは担任や校長に、どのような書類が必要か、どの条件を満たせば出席扱いになるのかをしっかり確認しましょう。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
不登校の理由が「体調不良」「精神的なストレス」「発達特性」などの場合、医師による診断書や意見書が必要となるケースがあります。
これは、出席扱いの制度が「心身の状況に応じた学習の継続」を前提としているためです。
医療機関のサポートがあることで、学校側も「家庭学習を通じて教育が継続されている」と判断しやすくなります。
すららのようなICT教材を使っていることを医師に伝えると、より具体的な意見書が書いてもらえることがあります。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
学校が出席扱いを認めるかどうかを判断する材料のひとつに「不登校の正当性」があります。
単に本人の意欲がない場合と、心身の状態によって通学が難しい場合では、対応が異なるからです。
そのため、必要に応じて、診断書を用意することが推奨されます。
診断書には、「現時点での通学が困難であること」や「家庭学習の継続が望ましい」という内容が含まれていることが理想です。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
診断書や意見書を依頼する際には、子どもの不登校の背景や家庭学習の状況を詳しく医師に伝えることが大切です。
「すららを使って毎日学習をしている」「本人は学習意欲を持っている」といった情報を医師に共有することで、より具体的な文言で意見書を書いてもらうことができます。
精神科・心療内科・小児科など、子どもの状態に応じた専門医に相談しましょう。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
すららでは、毎日の学習内容や進捗状況を記録として保存することができます。
このデータは、「家庭でどれだけ継続的に学習しているか」を学校に伝えるための重要な証拠となります。
出席扱いの申請では、このような学習証明が非常に重視されます。
コーチやサポートチームに相談すれば、出席扱いに適したレポートを出力する方法も教えてくれます。
定期的に学習履歴をダウンロードしておくと、必要なときにすぐ提出できるのでおすすめです。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
すららのマイページからは、学習時間・内容・正答率などをまとめたレポートをダウンロードできます。
このレポートは、担任や校長に提出することで、「家庭でしっかり学習している」という証明になります。
印刷して提出するのが基本ですが、PDFで提出できる場合もあるので、学校の方針に合わせて用意しましょう。
提出するタイミングも重要で、定期的な提出が望まれます。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
申請書自体は、基本的には学校側(校長先生)が作成しますが、内容を充実させるために保護者が補足情報を提供することが重要です。
たとえば「学習の目的」「本人の目標」「家庭でのサポート状況」などを添えて出すと、申請が通りやすくなります。
必要に応じて、すららの教材紹介パンフレットなどを添付しても良いでしょう。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
申請書類が整い、学校側が内容を確認した後、校長先生の承認を経て「出席扱い」として認められることになります。
場合によっては、教育委員会への報告や申請も必要です。
とくに自治体によって判断基準に差があるため、校長先生や学校事務と連携しながら進めるとスムーズです。
申請が通るまでには時間がかかることもあるため、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
最終的に出席扱いを決めるのは学校長です。
担任だけで判断できるものではないため、事前に校長先生に理解を得ておくことが大切です。
学校長が「学習が継続されている」「学習環境が整っている」と判断すれば、すららでの学習が出席扱いとして認められる可能性が高くなります。
担任を通じて説明するだけでなく、校長と面談を設けてもらうのも一つの方法です。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
自治体によっては、教育委員会への正式な申請が求められるケースもあります。
この場合は、学校が主体となって手続きを進めるため、保護者が単独で動く必要はありません。
ただし、必要な書類を早めに提出し、申請に必要な情報をすばやく提供することで、学校側の負担を減らすことができます。
すらら側のコーチやサポートチームに相談すれば、必要なデータの取得や資料の補助も受けられます。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します
不登校になったお子さんが「学校に通っていない=勉強していない」と思われることは、とても大きな不安です。
ですが、文部科学省の定める条件を満たすことで、ICT教材などを活用した家庭学習でも「出席扱い」として認定されるケースがあります。
「すらら」は、その出席認定基準に準拠した教材として、学校や教育委員会からも注目されている存在です。
ここでは、すららを通じて出席扱いを認めてもらうことのメリットについて、親子それぞれの視点から紹介していきます。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
内申点は進学においてとても重要な指標ですが、出席日数が大きく影響します。
不登校が続くと、どれだけテストの点数が良くても「欠席が多いから」と評価が下がってしまう可能性があります。
しかし、すららでの学習が出席扱いとして認められれば、出席日数を確保できるため、内申点の評価が著しく悪化するリスクを避けることができます。
特に中学や高校への進学を考えたとき、選べる学校の幅が広がるのは大きなメリットです。
子どもにとっても「自分の努力が無駄にならない」という安心感が生まれ、前向きに学習を続けることができるようになります。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
すららで学習していることが出席扱いになると、定期的な欠席日数が記録されるのではなく、出席としてカウントされるため、通知表や進学時の調査書に大きなマイナスが残りにくくなります。
中学・高校進学の選択肢が広がる
出席日数が確保されることで、内申点がある程度維持され、希望する学校への進学が現実的になります。
学力だけでなく「継続的に学習している姿勢」も評価されるのは、すららの強みです。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校期間が長引くと、「授業についていけないかもしれない」「もう取り返せないかも」という不安が親子ともに大きくなりがちです。
すららは完全無学年制の教材なので、学年に関係なく自分のペースで進められます。
たとえば、中学2年生で不登校になっても、中1の内容から復習し直すことができますし、得意な教科はどんどん先に進めることもできます。
この柔軟なシステムによって、「どこからやり直せばいいのか分からない」といった混乱を避けられ、学習への不安も和らぎます。
無理なく少しずつ進めることで「また勉強しよう」という意欲を取り戻すきっかけにもなります。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
学習の進度やカリキュラムは自分に合わせて自由に設計できるため、「もう遅れてしまった」という焦りを感じずに、自分のペースで取り組むことができます。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
「勉強している自分」「頑張っている自分」を実感できることで、子どもの自己肯定感が保たれやすくなります。
これは将来的な自立にも大きく影響する大切な要素です。
メリット3・親の心の負担が減る
不登校の子どもを育てる親にとって、最大の悩みの一つは「このままでいいのか」という不安です。
「学校に通えていない」「勉強が進んでいない」と感じると、親もプレッシャーを感じ、子どもにも無意識にそれが伝わってしまうことがあります。
すららを使って出席扱いになれば、「うちの子はしっかり学習を続けている」という安心感が得られます。
さらに、すららのコーチが保護者への相談対応も行ってくれるため、教育面の孤独を感じにくくなり、「うちだけじゃないんだ」と思えるのも心の支えになります。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
すららでは、学習の進め方や悩みに応じて保護者もコーチに相談できる仕組みがあります。
学校と連携しながら進める出席申請のフォローもあるため、親がすべてを背負い込まずに済むのが特徴です。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します
不登校のお子さんがすららを使って家庭で学習を進めている場合でも、それがそのまま「出席扱い」と認定されるとは限りません。
文部科学省の定めたガイドラインでは、出席認定の可否は学校長の裁量によるため、しっかりと準備をして学校側と連携することが大切です。
ここでは、すららを出席扱いとして認めてもらうために注意すべきポイントを紹介します。
学校側の理解を得るためのコツや、医師の診断書が必要な場合の対応、さらには定期的な連絡の重要性まで、実際に申請を進める際に役立つ具体的なアドバイスを詳しくまとめました。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
すららのようなICT教材を使った家庭学習が出席扱いになるかどうかは、最終的に校長先生の判断に委ねられます。
そのため、学校側の理解と協力を得ることが何よりも重要です。
担任の先生だけに話すのではなく、できる限り早い段階で教頭先生や校長先生にも相談し、全体で共有してもらうことが望ましいです。
また、すららが「文部科学省のガイドラインに沿った教材である」ことをしっかり伝えることも大切です。
公式サイトから出席扱いに関する情報ページを印刷して持参したり、実際の学習記録レポートを見せたりすることで、学校側も安心して判断しやすくなります。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
学校が最も気にするのは「家庭学習の正当性」です。
文科省に認められた教材であることを証明し、安心感を与えることで、出席扱いに対する理解を得やすくなります。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
担任だけでは判断できない場合もあるため、必ず管理職にも相談しましょう。
説明に必要なパンフレットや学習レポートなどを印刷して一緒に提出するのがおすすめです。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
不登校の理由によっては、家庭学習を「出席扱い」にするために医師の診断書や意見書の提出が求められることがあります。
特に精神的な不調や発達特性が原因で登校が難しい場合、小児科や心療内科、精神科などの医師から「学習を継続する必要がある」という内容の意見書をもらうことが出席扱いへの重要な材料となります。
このような書類は、学校や教育委員会が「家庭学習が必要である」と納得できる根拠となるため、手続きの初期段階で医療機関への相談を始めておくとスムーズです。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
病院によっては出席扱いの診断書を書いた実績がない場合もあるので、医師にあらかじめ「家庭学習を出席扱いにしたい」旨を丁寧に説明して協力をお願いしましょう。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
診断書には、「現在の通学状況」や「家庭学習の必要性」、「本人の意欲」なども記載してもらえると説得力が高まります。
可能ならすららの利用状況も伝えてください。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
子どもが前向きに学習に取り組んでいる様子を医師に伝えることで、より内容のある診断書を書いてもらえます。
家庭での学習の様子をメモして持参するとスムーズです。
注意点3・ 学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
家庭学習を出席扱いにしてもらうには、単なる自由学習や趣味的な勉強ではなく、「学校教育の代替としてふさわしい学習内容」であることが大前提となります。
文部科学省が定める基準としても、学習指導要領に準拠していることや、一定の時間・内容の水準が保たれていることが必要です。
すららは国語・数学・英語・理科・社会すべての教科に対応しており、AIを用いたつまずき分析や学習計画作成機能が充実しているため、まさにこの条件に適しています。
形式的に教材を使っているだけではなく、何をどのように学んでいるかが可視化されることもポイントです。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
家庭学習を出席として認めてもらうには、「ただの読書」や「市販ワークでの自習」では不十分です。
文科省の通知にあるように、学校の学習指導要領に沿ったカリキュラムに基づいて学んでいることが前提条件となります。
すららはこの要件をクリアしており、国のガイドラインに準拠した設計と、AIによる理解度チェック、苦手単元の補強が可能です。
さらに、各単元ごとに達成基準や評価が明確なので、学校側も学習の水準を判断しやすい仕組みになっています。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
出席扱いのためには、学習内容だけでなく、「どれくらいの時間を学習に費やしているか」も問われます。
文科省が目安として挙げているのは、1日2〜3時間。
これは1コマ45〜50分の授業を4〜5時間分に相当します。
もちろんすべて連続でやる必要はなく、すららのように10~15分で完結する構成で、朝・昼・夕と小分けにすれば無理なく実現可能です。
学習記録がシステム上に残るため、累積の学習時間をレポートにして学校に提出することもできます。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
出席扱いを受けるためには、「全教科をバランスよく学んでいる」ことも重要な条件です。
たとえば国語と英語だけでは偏りがあると判断され、認められないケースもあります。
すららは、国語・数学・英語・理科・社会の5教科に対応しており、それぞれの科目で苦手分析→復習→定着→応用というサイクルが構築されています。
また、学年を超えてさかのぼり学習・先取り学習ができるため、発達段階に応じて自然な形で全科目に触れることが可能。
家庭でのバランスの取れた学習環境づくりに最適な教材です。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
出席扱いにするかどうかの最終判断は、学校長に委ねられています。
そのため、家庭と学校の信頼関係が非常に重要になります。
どれだけ質の高い学習をしていても、学校との連携がなければ「家庭学習の実態が不明」とされてしまうことも。
すららには、学習記録や進捗データをレポートとして出力できる機能があり、これを活用することで学校への報告や説明がスムーズになります。
また、すららのサポート体制では、必要に応じてコーチが保護者の不安や質問に対応し、学校と連携しやすいようにアドバイスもしてくれます。
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
出席扱い制度を導入している学校の多くが、「家庭と学校で定期的に学習の進捗を共有すること」を条件としています。
これは、家庭だけで完結するのではなく、学校の教育活動の一環として扱う以上、継続的な連絡・報告体制が不可欠という考え方からきています。
すららは、保護者が子どもの学習状況を簡単に確認でき、レポート出力もワンクリックで可能なため、学校に提出する資料づくりが非常に楽です。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
学校によっては「毎月末に学習報告をください」と指定されるケースもあります。
すららでは、月間の学習時間、進捗、理解度、弱点科目の改善状況などがまとめられたレポートを出力できるので、そのまま印刷して学校に提出できます。
これにより「どのように学習しているか」が視覚的に伝わりやすく、担任や校長も判断がしやすくなります。
報告の手間が省けるのは保護者にとっても大きなメリットです。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
制度の運用に際し、学校側が「家庭での学習状況をもう少し詳しく知りたい」と判断した場合、面談や家庭訪問をお願いされることがあります。
すららのようなオンライン教材であっても、日常的な取り組みや保護者の関与があるかを確認したいという学校側の意図があります。
このときも、すららで記録された学習履歴を見せることで、日々の学習の積み重ねが証明され、家庭の真摯な姿勢が伝わりやすくなります。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
出席扱いをスムーズに認めてもらうためには、「学習の報告を受け取る側=学校」の立場にも配慮した対応が求められます。
担任の先生とは月1回の連絡だけでなく、できれば週1回、メールや電話で状況を共有すると効果的です。
「今週は数学に力を入れています」「英語が少し苦手なようです」といった内容を簡潔に伝えるだけでも、教師側の安心材料になります。
すららは記録が残るので、話のネタにも困りません。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
地域によっては、出席扱いの判断に教育委員会の承認が必要なこともあります。
これは学校単体では判断が難しいケースや、制度のガイドラインに厳格なエリアで見られます。
この場合、保護者が提出する資料は一層丁寧に準備する必要があり、内容も具体的でなければなりません。
すららは、文部科学省の通知に則って設計されており、教育委員会への提出に使える公式な実績や資料が充実しています。
事前に学校と相談しながら準備を進めるのがポイントです。
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
教育委員会への申請書類は、自治体ごとに様式や求められる情報が異なる場合があります。
焦って独自に用意するのではなく、まずは学校と相談し、必要書類の形式や記載内容をしっかり確認するのが重要です。
すららの公式サイトやコーチサポートでは、こうした申請に使える資料テンプレートを提供していることもあります。
書類作成に不安がある場合は、すららのサポートチームに相談してみるのもおすすめです。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します
すららを使って家庭学習をしている不登校の子どもが「出席扱い」と認定されるには、いくつかのポイントを押さえて学校側にうまく働きかけることが大切です。
制度自体は存在していても、学校によって対応はバラつきがあり、具体的な成功例を示したり、本人の学習意欲を伝えたりすることが信頼につながります。
ここでは、実際に出席扱いを目指すご家庭が意識すべき成功のポイントについて詳しく紹介します。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
出席扱いの制度は知っていても、学校側が実際に導入しているかどうかは別の話。
前例がない場合、学校側も慎重になりがちです。
そこで効果的なのが、すららを使って「他の学校で出席扱いになった」事例を提示すること。
これはとても説得力があります。
すららの公式サイトには、全国の学校や教育委員会と連携して成功したケースの実績が掲載されているので、それを印刷して資料として持参するだけでも、学校側の理解が深まりやすくなります。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
学校は「初めての事例」に対して慎重になりがちです。
しかし、全国で実際にすららを活用して出席扱いとなったケースを紹介することで、安心材料になります。
すららの公式サイトには複数の導入事例が掲載されているので、それを活用して「うちの子も同様の支援を受けられる可能性がある」と具体的に伝えましょう。
実例に勝る説得力はありません。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
すららの公式ページでは、実際に出席扱いを実現した学校の一覧や、教育委員会との連携実績が紹介されています。
これを印刷して担任の先生や校長先生に見せれば、話の理解もスムーズになります。
「すでに認められている教材なんだ」という安心感を学校に与えることで、前向きな対応を引き出しやすくなります。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
出席扱いの申請では、「親ががんばっている」だけでなく「子ども自身の学習意欲」が大きなポイントになります。
たとえば、学習を続けている様子や、感想を書いたメモ、取り組んでいる画面のスクリーンショットなど、子どもが主体的に学んでいることを伝えることで、学校の信頼も得られやすくなります。
また、面談の場ではできる限り本人も参加し、「がんばっている姿勢」を直接見せることが大切です。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
たとえば「今日〇〇を頑張りました」「△△をもっとできるようにしたい」といった簡単なメモや日記で構いません。
形式にこだわるよりも、本人の声として伝わることが重要です。
子どもの言葉で「勉強をがんばっている」ことが伝われば、学校側の心証もよくなり、出席扱いの判断が前向きになりやすいです。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
保護者のみの説明よりも、本人が「自分の言葉で」話すことで、説得力が一気に増します。
たとえば「勉強は苦手だけど毎日すららをやっている」など、正直な気持ちを話すだけでも十分。
緊張して話せなくても、学習中の様子を動画で見せるのも一つの方法です。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
出席扱い制度の中でも特に重視されるのが「継続性」です。
一時的に頑張るのではなく、習慣的に学んでいることが評価されます。
そのため、無理のある計画では続きません。
すららではプロのコーチが学習計画を一緒に立ててくれるため、子どものペースに合ったプラン作成が可能です。
長期的に無理なく続けられる計画でこそ、学校にも信頼され、出席扱いが認められやすくなります。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
「1日3時間やる」といった理想的な目標も、続かなければ意味がありません。
1日20分でも、毎日できることのほうが圧倒的に価値があります。
すららでは子どもの集中力や得意不得意に応じて、個別の学習設計が可能。
無理のない目標設定で、継続の実績を積み上げていくことが大切です。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
親だけで学習スケジュールを立てるのは意外と難しく、途中で崩れてしまうことも多いです。
すららの専任コーチは、子どもの性格や学習履歴を見ながら、現実的なスケジュールを提案してくれます。
コーチのサポートがあると「第三者の視点」でスケジュールが見直せるため、保護者の精神的負担も軽くなります。
ポイント4・:「すららコーチ」をフル活用する
すららの最大の強みの一つが、学習計画や進捗の管理をしてくれる「すららコーチ」の存在です。
特に出席扱い制度を利用したいときには、コーチのサポートが大いに役立ちます。
どんなレポートを出せばいいか、どのタイミングで学校と連携すべきかなど、保護者が一人で悩まずに済みます。
学習のフォローだけでなく、制度申請の実務的な部分まで見てくれるのは非常に安心感があります。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
すららでは、出席扱いに必要な学習履歴や進捗状況をもとにした「学習レポート」の出力が可能です。
さらに、必要に応じてコーチが「どういう形で提出するとよいか」「学校に説明しやすいポイントは何か」などもアドバイスしてくれます。
学校への提出書類を整えるのは大きなストレスになりがちですが、専門知識のあるコーチのサポートで、保護者の負担が大幅に軽減されます。
すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。
でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。
時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。
イライラして何度も怒ってしまっていましたが、
すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。
完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。
タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。
キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。
教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。
他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問
「不登校だけど、出席日数が足りるか心配」「すららを使っていれば出席扱いになるの?」という声が増えています。
この記事では、タブレット学習教材『すらら』がなぜ出席扱いになるのか、どんな条件があるのか、また具体的な申請方法や注意点なども含めて徹底解説します。
加えて、よくある質問への回答をQ&A形式でまとめているので、実際に導入を考えているご家庭にはとても参考になります。
すららが不登校支援教材としてなぜ評価されているのかを、口コミや制度の観点からも一緒に見ていきましょう。
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
「すららがうざい」という口コミは一部に見られますが、その多くは“連絡が多い”“コーチのフォローがしつこいと感じた”などの声です。
実際には、これは「手厚いサポート」の裏返しであり、保護者にとっては安心材料となるケースも多いです。
子どもが自発的に学習できるタイプの場合、サポートが過剰に感じられることもありますが、継続や習慣化を助けるための丁寧なフォローである点を理解して利用すれば、むしろ大きなメリットに変わります。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららには「発達障害専用のコース」は存在しませんが、学習内容やサポート体制は発達障害のある子どもにも配慮された設計になっています。
料金プランも一般と同じで、3教科・4教科・5教科の各コースから選択可能です。
入会金は7,700円〜11,000円、月額は8,228円〜10,978円(コースや契約期間により変動)となっています。
ADHD・ASD・LDの特性に合わせて学習計画を立てられるのが魅力です。
関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
はい、すららは文部科学省が定めるガイドラインに則っており、条件を満たせば「出席扱い」として認定される可能性があります。
必要なのは、学習の記録や学習の質が証明できること、そして学校との連携です。
すららでは、専任コーチが保護者や学校とのやり取りをサポートし、学習レポートも自動で出力されるため、申請手続きがスムーズに進めやすくなっています。
関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららでは、入会時にキャンペーンコードを入力することで、入会金無料や月額割引などの特典が受けられることがあります。
コードは株主優待・資料請求・説明会参加者などを対象に配布されることが多いです。
入力方法は、公式マイページや申込フォームの「キャンペーンコード入力欄」に該当コードを入力するだけ。
利用には有効期限があるため、取得後は早めの利用をおすすめします。
関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららの退会は「解約」と「退会」で異なります。
解約は利用を停止する手続きで、退会はアカウント情報・学習データをすべて削除する手続きです。
解約は電話(すららコール)でのみ受け付けており、毎月25日までに連絡すれば翌月から解約が有効になります。
退会したい場合は、解約完了後にサポートへメールまたはフォームから連絡します。
休会という選択肢もあるので、再開の可能性がある方は慎重に検討しましょう。
関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららでは、入会金と月額受講料以外に基本的に追加料金はかかりません。
教材費・タブレット代なども不要で、すべてオンラインで完結します。
ただし、家庭にインターネット環境と端末(パソコンまたはタブレット)は必要です。
オプションで英語4技能コースなどを追加した場合は、追加料金が発生することがありますが、事前に明確に説明されるので安心して利用できます。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららでは、1契約につき1アカウントが付与され、基本的には兄弟で共有することはできません。
しかし、「兄弟追加」キャンペーンなどを利用すれば、2人目以降の入会金が無料になる特典が適用される場合があります。
進度を個別に管理したい場合は、別々にアカウントを作成することが推奨されます。
兄弟利用のニーズがある家庭は、事前に公式に問い合わせて、最適な契約方法を確認するのがベストです。
すららの小学生コースには英語はありますか?
はい、すららの小学生向けコースには英語も含まれています。
ネイティブ音声のリスニング機能、単語や文法の理解をアニメーションで視覚的に学べる構成になっていて、初めて英語に触れるお子さんでも安心して学べる設計です。
また、スピーキング練習や発音チェック機能もあるため、小学生の段階から「聞く」「話す」「読む」力をバランスよく育てることができます。
英検や中学英語への準備にも最適です。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららのコーチは、子どもの学習習慣を定着させるために、定期的にフォローアップを行ってくれます。
学習ペースや目標の設定、つまずきポイントの分析、保護者への進捗報告など、学習に必要なサポートを幅広く提供してくれる存在です。
発達障害のある子に対しても、専門的な配慮をもって接してくれるため、「親がつきっきりで教えるのが難しい」という家庭にとっては大きな支えになります。
参照:よくある質問(すらら公式サイト)
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました
「不登校の子どもにタブレット教材を使わせたいけど、どれがいいのか分からない」「出席扱いになる教材ってあるの?」と悩むご家庭は少なくありません。
そこで今回は、【すらら】がなぜ不登校支援に強いのか、他の代表的な家庭用タブレット教材(例えばスマイルゼミ・スタディサプリなど)と何が違うのかを比較しながら紹介します。
すららの特長である「文科省ガイドラインに準拠」「学習記録の提出」「コーチによる支援」など、出席扱いの要件を満たしやすい仕組みがどのように構成されているのかもわかります。
他教材との違いを理解することで、お子さまの学びを支える最適な選択ができるはずです。
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ
すららは、不登校の子どもが自宅で学びながら「出席扱い」にしてもらえる可能性がある数少ないタブレット教材の一つです。
ただし、「ただ使っているだけ」では出席扱いにはなりません。
学校や教育委員会にきちんと学習状況を報告し、文部科学省のガイドラインに則った手続きを踏む必要があります。
このセクションでは、すららで出席扱いを認定してもらうための制度の概要、申請の流れ、そして見落としがちな注意点までを、学校とのやり取りのリアルな視点も交えて解説します。
「何から始めたらいいの?」「どんな書類が必要?」といった疑問をまるごと解消し、すぐに動ける状態へサポートします。
